子供たちが靴のかかとを踏んでしまう問題、お困りではありませんか?
私は朝、こどもを学校へ送り出すとき。
夕方、学童まで子どもを迎えに来たとき。
「子どもの靴のかかとが踏まれている」状態を目撃すると、親である私の心がモヤモヤします。
もはや、子どもは、
「靴のかかとは踏まないようにね」
と、親や学校、学童の先生方に、散々言われてきているので、今さら耳を貸さず、軽やかにスルー。
この声かけ以外の切り口で、なんとか解決しなければ!と思い、対策を考えました。
他にも、その小さな足を守るための正しい靴の選び方、お手入れの方法、そしてかかとを踏まないための楽しい習慣の作り方など、ご紹介しますね
そもそも、なぜ靴のかかとを踏んではいけないのか?
靴をきちんと履かないと、ケガをするからです。
ほかにも、いくつか理由があるので、ご紹介しますね。
理由① 靴の寿命が短くなる
まず、靴の寿命について考えてみましょう。
かかとを踏むことで、靴の形が崩れたり、素材が早く摩耗したりします。
特に子供靴はデリケートなので、このような扱いは、靴の寿命を大幅に縮めてしまうことがあるんです。
理由② 足への悪影響
次に、足への影響です。
靴のかかとを踏むということは、つま先に重心を置いて歩いているということですね。
つま先に重心を置くということは、すねに余計な力が入ってしまうことになります。
余計な力が入ると、すねの部分の骨を痛めてしまうのです。
すねの部分の骨を痛めると、夜も眠れないほどだそうですよ。
子供の足は成長途中なので、特に気をつけたいポイントですね。
理由③ 歩き方の癖
さらに、歩き方の癖にも注意が必要です。
かかとを踏んで歩く癖がついてしまうと、正しい歩き方が身につかないことも。
これが大人になっても続くと、腰痛や肩こりなどの原因にもなりかねません。
理由④ 見た目の問題
最後に、見た目の問題も忘れてはいけません。
かかとを踏んで歩く姿は、どうしてもだらしなく見えてしまうことがあるんです。
おしゃれな靴を履いても、この歩き方では台無しになってしまうかもしれませんね。
子どもが靴の かかとを踏まなくなる3つの対策
対策①→靴を洗う
【靴が汚いままだと、扱いもぞんざいになりがち】
子どもでもできる「靴のお手入れ」は、この3つ。
①汚れたら洗う
②洗う曜日を決めておく(土曜日など)
③匂いに気づくということ
大人になったからといって、急に持ち物を大切にしたり、身の回りの物を管理したり出来るようになるわけではありません。
子どものうちから、繰り返し「訓練」する必要があるのですね。
「足元をみる」という言葉は、「人の弱みにつけこむ」という意味があります。
江戸時代の頃、人を籠に乗せて担ぐ仕事をしている人が、歩いている旅人の足元の疲れ具合を見て、高額な料金で交渉したということに由来するそうです。
、、となると、手入れされた綺麗な靴を履いていたり、
人の家にお邪魔するとき、雨で靴が濡れてイヤな匂いにならないように雨靴を履いたり、替えの靴下を予備で持つといったりすることは、相手に対して礼を尽くしていることにもなります。
靴や身の回りが汚いと、
自分の持ち物の管理が出来ないということで、お金持ちになれなかったり、
相手を大切に出来ないということで、仕事も上手くいきません。
ですが、やっぱり子どもにとって、履きやすい靴というのがあるのかもしれない。
靴が小さくなったから、かかとを踏んでしまっていることに、子ども自身が気づいていないだけなのかもしれない。
対策②→履きやすい靴を探す
「スリッポン」 →スリップ オン シューズの意味で、足を靴にすべらせるようにして履くことが出来る靴のこと。
|
|
この上履きは、子どもの踵(かかと)踏み付け防止として、とがり過ぎず丸過ぎない程度の樹脂の出っ張りをつけ、かかとを踏みにくくする工夫がされています。
かかとを踏んで5分ほどすると痛くなり、違和感を感じるそうです。
|
|
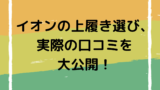
対策③→「次の靴は新品では買わない!」、「中古の靴で良し!」と、決める!
過去に、どんな靴が買いたいか子どもと一緒に買いに行った時、子どもが自分で選んだはずの新品の靴。
それを最後まで大切に出来ないのなら、
「新品を選ぶ理由もなし!」
自分で選んだことも忘れてしまうってことは、靴を含め、物を大切にする心をしっかり伝えなければいけないと思いました。
【まとめ】
子どもが靴の かかとを踏まなくなる3つの対策として、
①靴を洗う
②履きやすい靴を探す
③「次の靴は新品で飼わない」、「中古の靴で良し!」と、決める!
を、ご紹介しました。
「3つの対策のうち、1つだけやってみる」というより、3通りの方法で「靴やものを大切にする心」を伝えていくということを繰り返していくことかなぁと思います。
ほかにも、子育て情報を紹介しています(^^)/
こちらもどうぞ☆


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/312e63cb.29fae9b0.312e63cc.ffa2c399/?me_id=1311314&item_id=10032615&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkutsu-collection%2Fcabinet%2F1%2F12%2F1288%2F1288-0024-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ee624bf.dd13d787.1ee624c0.4c7d31b0/?me_id=1221738&item_id=10031397&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyoikutsu%2Fcabinet%2Fitem05s%2F1121143.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


